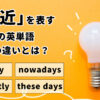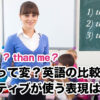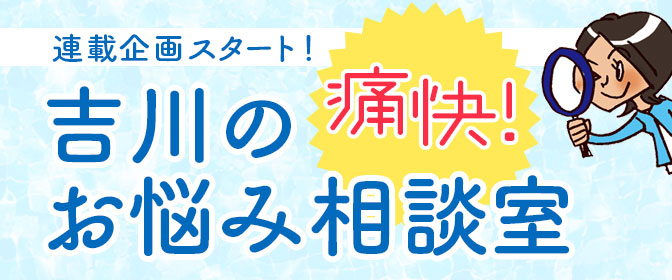【小学生】国語が苦手な子どもの特徴と、3つの間違いポイントとは?
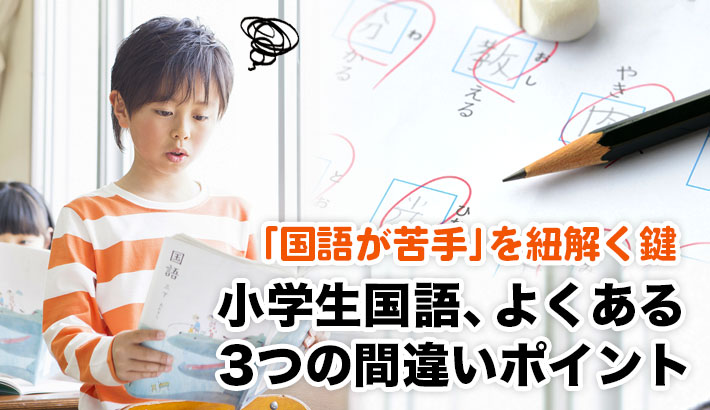
「本を読まない子が増えた」「日本人の国語力が低下している」「英語より国語が先でしょ」など、日本人の国語力の低下を憂える議論がなされて久しい昨今。ですが、いざわが子が「国語が苦手」という状態になると、保護者の方も「このままで大丈夫か?!」と不安になってしまうことでしょう。
しかし、「国語が苦手」と嘆く前に、「どうすればいいの?」と悲嘆に暮れる前に、まずお子様の状態を、落ち着いて見極めることが重要です。
さて今回は3回に分けて、ご家庭でもできる、国語の苦手確認法と苦手を克服する方法をお伝えします。第一回目は「国語が苦手」ということについて考えていきましょう。
国語は二択で迷い、間違いやすい教科
記号選択問題で、「2つまで絞れるけど、最後のひとつで間違いを選んでしまった」という経験はありませんか?
どんな教科でも、「わかっている」から「できる」わけではありません。特に国語は、「わかる」レベルと「できる」レベルの隔たりが大きい教科です。もっと言えば「点になる」レベルとの隔たりが他教科に比べて大きい教科です。
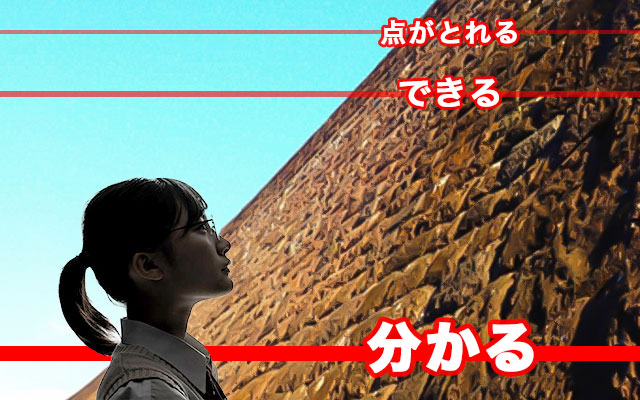
つまり、頭の中で「ああ、こんなことを言っているな」とわかったつもりでも、記号選択問題で2つまでは絞れるけど、最後の1つで間違えるということが起きやすい教科なのです。
しかし、そのようなお子様は、本当に「国語が苦手」なのでしょうか?「国語力がない」のでしょうか?
答えは否です。
「問題を間違えた(国語の点数が低い)」=「国語が苦手」「国語力がない」ではありません。
相手は「日本語」です。
まずは腰をすえて、「何ができていないのか」「なぜ、できていないのか」を分析してあげてください。
以下、「できていない」ように見える症例を3つ見ていきたいと思います。
国語が苦手?勘違いが生まれる3つの症例
症例① そもそも文章を読んでいない
「文章を読んでいない」=「国語力がない」ではありませんね。
この場合は「勉強習慣」がついていない、あるいは「あきらめやすい」という心理的な問題と言えます。
これに当てはまるお子様は、親がいっしょに文章を読んであげたり、あるいは、音読しているのを聞いてあげたりしてください。
以下の記事でも、音読の大切さをお伝えしています。
症例② 問題をよく読んでいない、理解していない
答案を見たとき、問題の意図をとらえていない答案、問題の指示に従っていない答案がよく見られます。
「〜は誰ですか?」に対する答え方
例えば「〜は誰ですか?」という問いに対し、「走るメロス」が答えなのに、「メロスが走る」と答えている。
つまり、「誰?」という問題に対すると答えは「名詞」のはずなのに、「走る」という動詞で終わっているのです。これでは、マルをもらうことはできません。
「〜はなぜですか?」に対する答え方
また、「〜はなぜですか?」と聞かれているのに、「~から。」で終わっていないという回答もよく見かけます。
あるいは、そもそも「~から」で終われる解答になっていないなど、問題がこう答えてほしいと示しているものに対して、答えておらず、点になっていない例もあります。
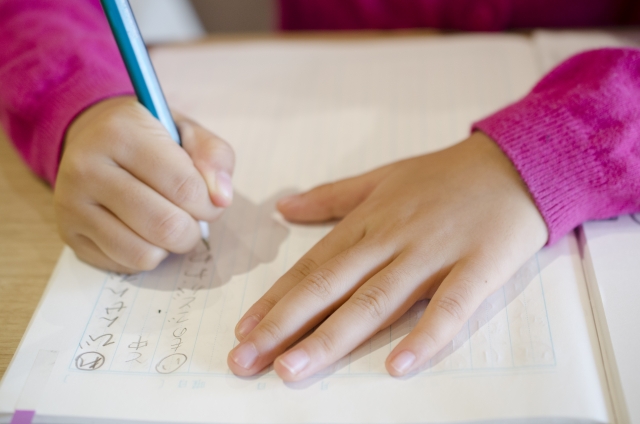
これらはどちらも、文章自体の読解ができていないのではありません。
問題に対して、適切に答えられていないのです。
「問題に対して適切に答える」ためには、やはりその練習をする必要があります。
症例③ 勘で解いている
記号を選ぶ問題によくありますが、文章の内容は、「こんなもんかな」と分かったつもりで、いざ記号を選ぶときも「これっぽいな」で選んでしまうことがよくあります。
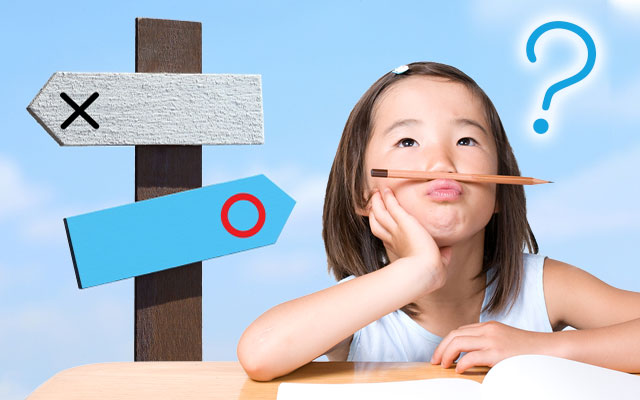
このような当てもの感覚で問題を解いていると、いつまでたっても国語の成績はあがりません。いくら国語の勉強をしたとしても、運は身につかないのです。
この場合は問題への取り組み方を改めなければなりません。
しかしながら、やはりこの状況も、「国語力」が直接的に関わっているのではありません。
以上のように、一見、「国語が苦手」と見える場合も、実は「国語力がない」と言えない場合が多いことが分かります。
つまり、国語の場合、「国語の点数が低い」=「国語が苦手」「国語力がない」ではなく、単に「取り組み方の問題」「分かっていても、点にできないという問題」が多いのです。
お子様の性格で分かる、国語力の違い
おしゃべりな子
もし、お子様がいわゆる「おしゃべり」「口達者」であれば、基本的に国語力には問題がないと思ってもらって差し支えはないと思います。なぜなら「おしゃべり」であれば、頭の中に日本語の基本的な構造ができているからです。
それでも点数が取れない場合は、それを様々な理由(とくに前半で書いたような理由)から、解答用紙上に発揮できていないのです。
寡黙な子
一方で、お子様が寡黙な場合は注意が必要です。
なぜ、寡黙なのか。
ひとつは性格がおとなしいという場合があります。この場合は、頭の中に日本語の構造ができているかどうか、注意深く見守る必要があります。
もうひとつは、「頭の中に日本語の構造のストックがない」から話せない。つまり、「話すネタがない」から「寡黙」になってしまっている場合は、「国語力が不足している」傾向にあります。

なぜなら「国語力」とは、いかに日本語の文章のストックが頭の中にあるか、またそれをいかに口頭で、あるいは紙面上に表現できるかということだからです。
お子様の国語力をつけるおすすめの方法
それでは、「国語力をつける」ためには、どうすればよいでしょうか。
現時点の「お子様の国語力」は、これまでの人生においての言語生活の集大成であると言っても過言ではありません。しかし、今からでも国語力を鍛える方法はあります。
子どもと話をする。承認し、質問する。
まず一つ目は子どもとしっかりコミュニケーションをとることです。
先述のように、おしゃべりをすることで日本語の基本的な構造ができ、言語化能力にも好影響を与えます。
これまで、お子様とよく会話してきましたか?
いろいろな内容の話をしてきましたか?
その中に、ちょっと難しい言葉を混ぜて話してきましたか?
今からでもお子様と話をする機会を作ってください。
そして、話を聞き、「うん、そうだね」と承認した上で、質問を投げかけてあげてください。学校のこと、習い事のこと、好きなテレビのこと、何でも良いのです。

その中で、ちょっと難しい言葉、ちょっと難しい表現を入れてあげてください。それが分からないなら、分からないでいいのです。その積み重ねが大事です。「どういう意味?」と聞いてきたら、親身に答えてあげてください。
答えるのが難しい場合は、辞書でいっしょに調べるのがベストですが、辞書がなければ、今はスマホで簡単に検索できます。
- 子どもが話をしてきたら、まずは聞き役に回る
- 「うん、そうだね」とまずは承認してあげる
- 親からも質問を投げかける
- 会話の中に子どもにはちょっと難しい単語や表現を入れる
- その単語や表現について興味を持ってきたら、親身に答えてあげる
さて、今回はここまで。
国語力をつける方法二つ目「読書」についてのお話は次回の記事でお伝えします。







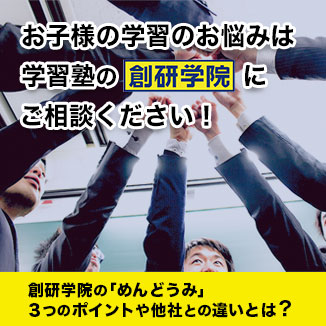
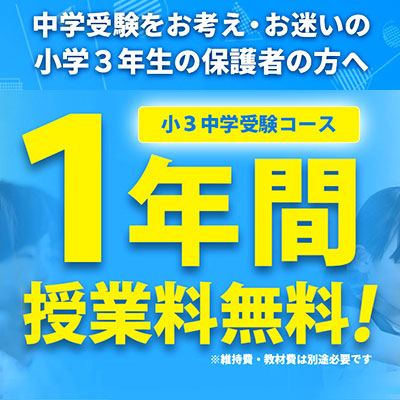
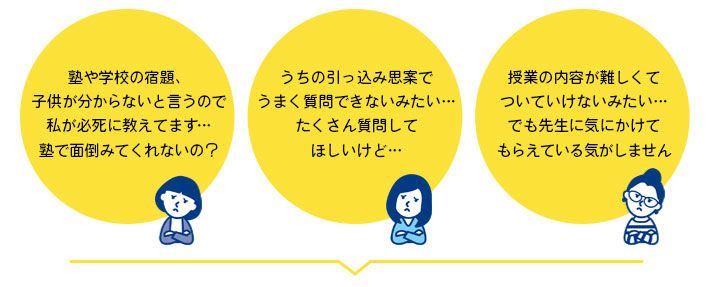
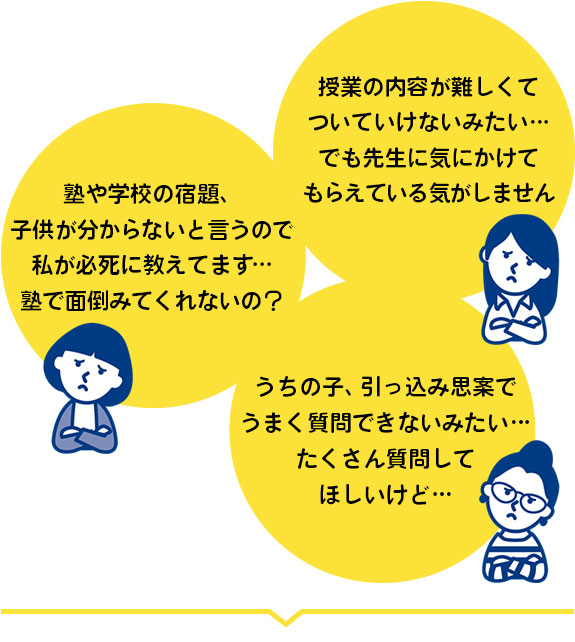
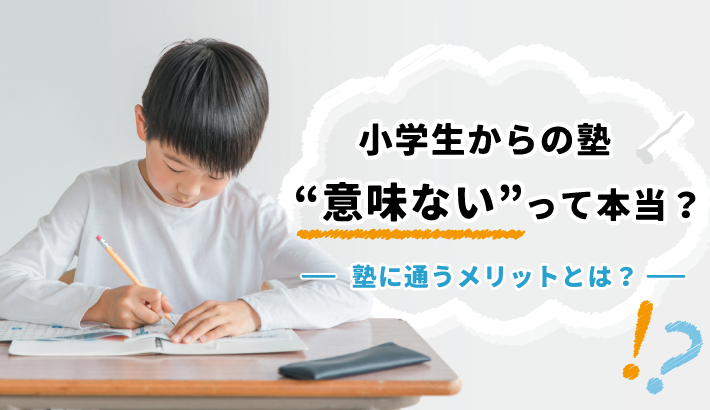
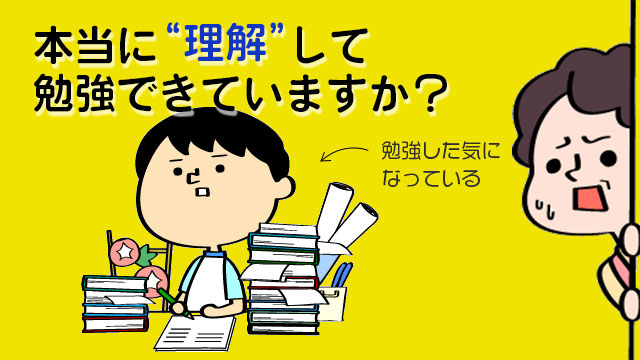

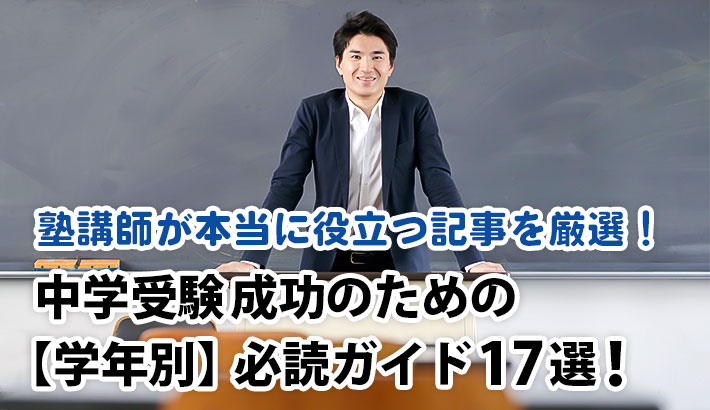
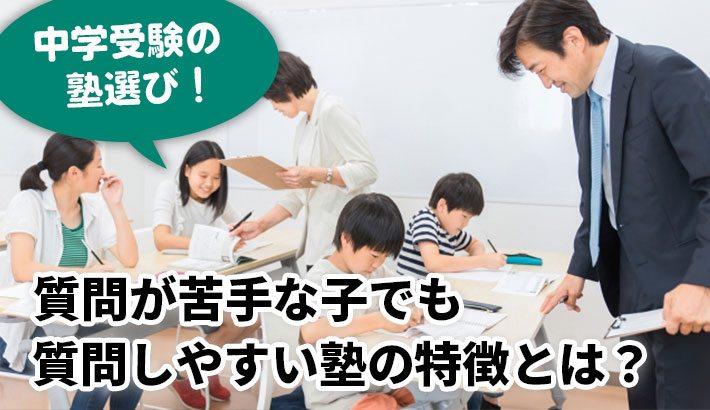


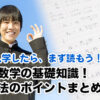

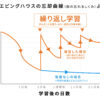
![中1理科 “食塩水”の攻略[理論編] 動画で解説](https://mana-brain.com/wp-content/uploads/2020/07/shokuensui-100x100.jpg)